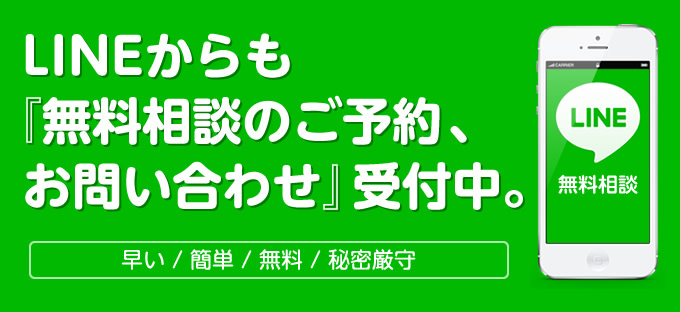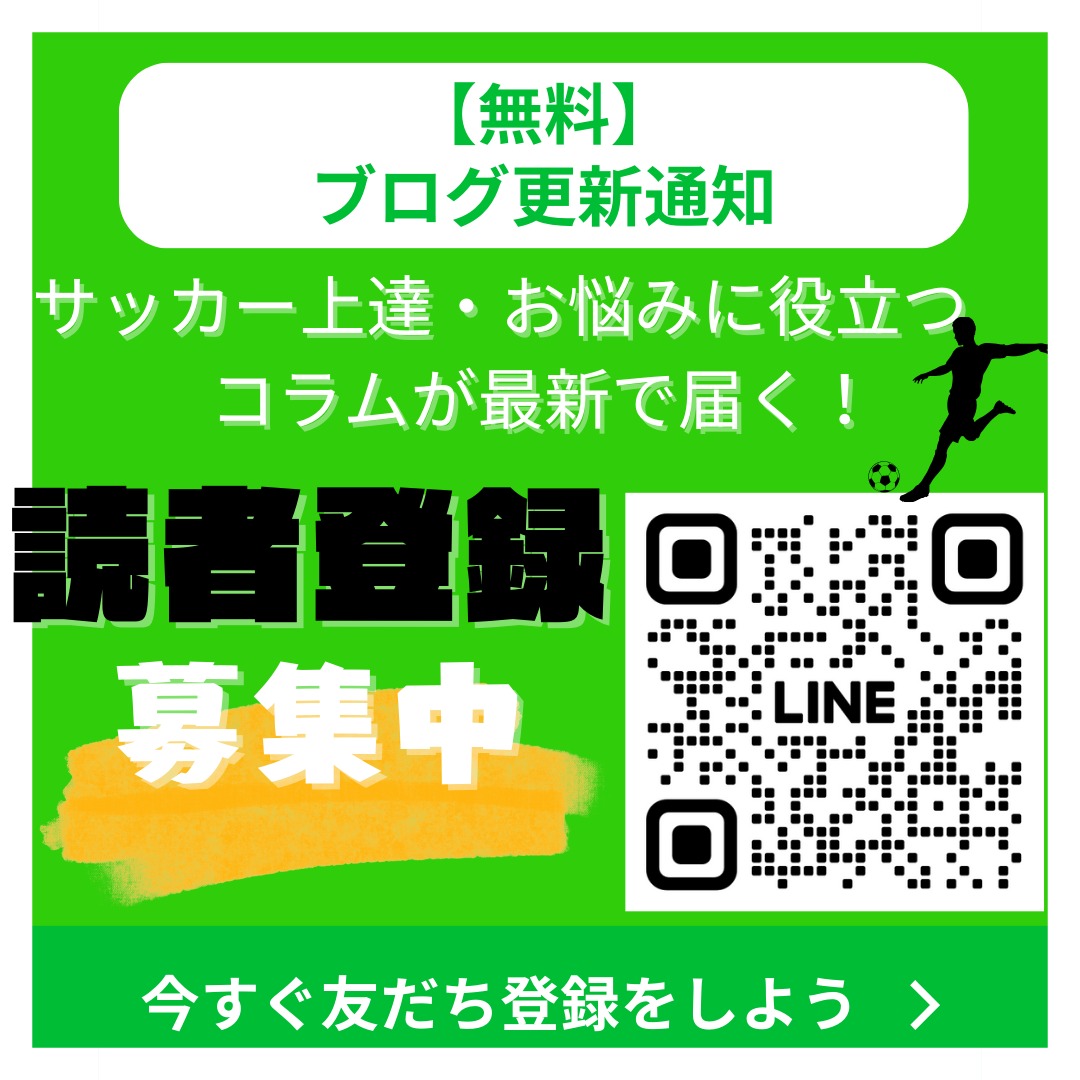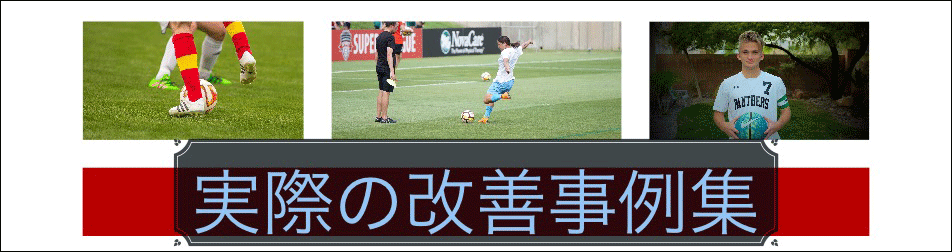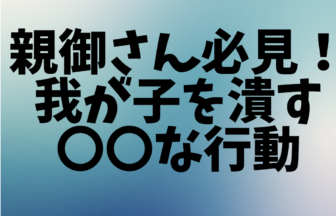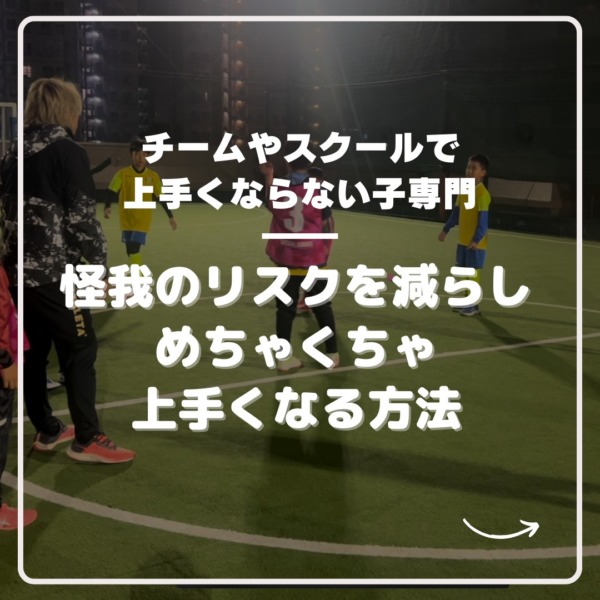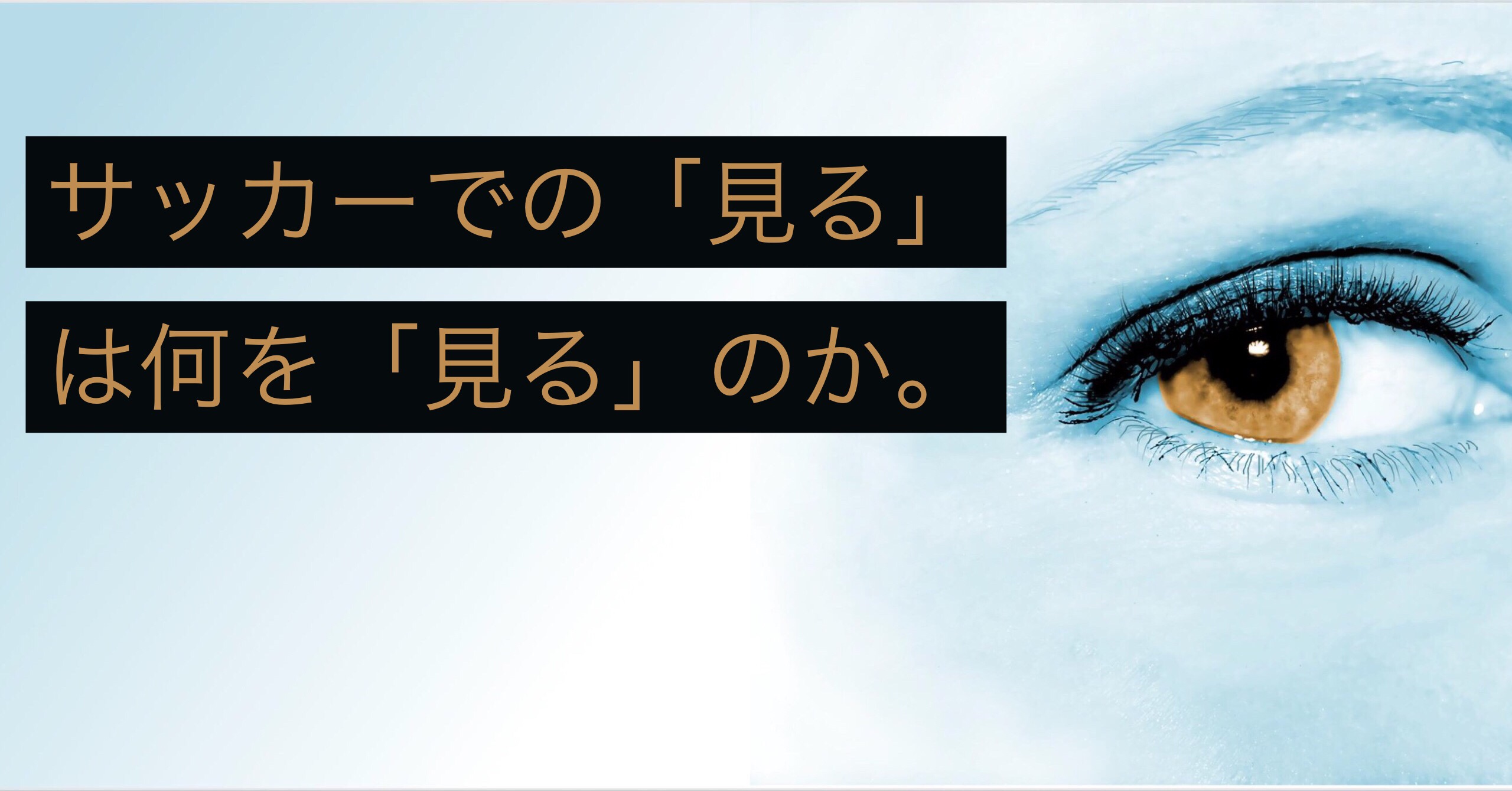
こんにちは
谷田部です。
最近のレッスンやゲーム会で気になった
「コミュニケーション」と「見る」
この関係性は、切っても切れない。なと改めて感じます。
「コミュニケーション」と「見る」と言葉で言えば簡単ですが
もっと深く子供達の中を見ていくと非常に様々な発見があります。
主張は出来るようになった。でも相手に受け入れられない。という問題
直近のゲーム会では、お互いが言いたいことを相手に伝えることができるようになってきました。
それでも自分の言いたいことをお互いが言っているだけで一向に受け入れられない。
結局一方的に言い続けるか、「なんでだよ」と最終的には諦める。
ではなぜこのようなことが起きるのか?
答えは簡単です。
見ていないのです。
でも本人は見ているつもりです。
では何を見ていて何を見ていないのか・・・
~ここから会員限定~
会員登録はこちら
答えは
「相手の状況」と「態勢」「心理面」「性格や特徴」「スキルレベル」と言った部分です。
相手の状況とスキルレベルや態勢、心理面、そして性格や特徴
これらを見た上で声がけは変わってくるはずです。
結果見ていたのは”ボールのみ”相手のことなんて一切見ていない。
具体的状況から
例えば今回あったのは
「出せよ」「なんで前に出さないんだよ」という場面
これを繰り返していて言い合いになっていました。
「出せねえよ!」
客観的状況はこうです。
顔が上がっていない、首を振っていない。ボールしか見ていない。(態勢)
焦っている(心理面)
プライドは高い、言われている相手よりも上級生(性格や特徴)
顔を上げてボールコントロールにまだ自信がない(スキルレベル)
ここに「出せよ」なんて上から厳しく言い続ければ「出せねえよ」になるのは当然です。
ではどのように言えばよかったのか?
焦っている状況です。「落ち着け」と一言言ってあげる。
または次の時には「簡単に俺に出していいよ」
成功すれば「ナイス」失敗すれば「次!」
簡潔に状況に応じた声がけをしてあげること。
上からひたすら出来ていない相手に言い続けても
それは受け入れません。
パワハラ上司や先生と同じです。
相手へのアプローチを変えること。
もちろん自分がある程度できることが前提です。
自分が失敗すれば認め「悪い!」くらい言えるかどうか。
それぞれがリーダーシップを発揮し、マネジメントしていく。
サッカーは集団スポーツに見えますが、そうした能力を持った「個人」が集まったにすぎない個人スポーツです。
いわばみんな社長で部下です。(笑)
使い使われる。の切り替えと判断と気遣いが求められるのです。
セレクションで受かるのは極端に言えば各チームの「キャプテン」
気遣いが出来すぎても困るのですが
セレクションで各チームが欲しいのは各チームでリーダーシップを取れるようなキャプテンタイプです。
これをよく使われる表現で言うと
「考えられる子」や「大人」
です。
要するに自分のことも出来る。そして気遣いもできる。そんな子が理想なんです。
そしてもう一つ言えば自分で行かなければならない時にいける「傲慢さ」や「厳しさ」に徹することができる。
自分をマネジメントできる”スイッチ”を切り替えられる子です。
サッカーのフィールドはいわば”舞台”です。
演じ、魅せることが求められるのです。
その中で普段と違う自分に切り替えるのは当たり前に求められることなのです。
コミュニケーションの取り方も学んで欲しい
相手を理解しようとすることから始まると思います。
そして私自身も誰かの真似や本などから学んだ知識を参考にしているのは間違いありません。
ゲーム会などで私自身もゲームによく参加しますが
そうした時の身振り手振りや声がけなども真似て持って帰って欲しいと思います。
私自身コーチとしてと言うよりも1プレーヤーの視点でしか基本的に話はしていません。
それは個人レッスン時も同じです。
だから私自身、コーチ。と呼ばれても今なおピンとこないことが多いです。(笑)
最近のサッカースクールはボールコントロールや動き方を教えればいいと思いますが
本当に大切な部分にコーチたち自身も気づいていない方が大半です。
本当はそうではないはずなんです。
高いレベルのサッカーの現場で求められるもの
なぜなら実際の試合では相手チームの11人の特徴(利き足・プレースタイル・主従関係・性格)を開始5分で把握することから始まるからです。
これがわからないようなコーチは、ボールとしか戦っていなかった。レベルに過ぎません。
相手を理解し、特徴を掴んでいく。そうしたものを「見る」観察することから
「コミュニケーション」は始まっていく。
サッカーが!
と言うよりも人としての「思いやり」や「気遣い」を持ち「強さ」と「厳しさ」を持つこと。
「サッカー」に固執していると見えなくなるかもしれませんが・・・
コミュニケーション能力をつけるとどこでも力を発揮しやすい
一歩引いて客観的に見ること。
これがリーダーシップや信頼にも繋がっていきます。
結果周りの人間が生き生きとし、自分自身をも生かしてくれる。
回り回って「サッカーが楽しい」さらに楽しくなってもっと・・・と言うサイクルが生まれます。
自分を理解し、相手を理解する。
をおざなりにしない。
そうするといいプレーが自然と増えてくるのです。
私が本当に伝えたいこと
「人間形成」なんて大きなことは言いません。
もっと大きく言えばたまたまサッカーだっただけです。
振り返って見れば
お互いが気持ちよく楽しく出来る大人が一人でも多くなって欲しいな。
と思っているに過ぎないかもしれません。
私自身レッスンもゲーム会も毎回楽しませてもらっています。
でもこうした子達が強いチームのコーチからも評価されるのです。
こいつと3年間サッカーやりたいな。と
良い刺激を得られる環境をサッカー家庭教師ではご用意しています。
まずはご相談ください。
今現在のサッカーの上手い下手。は関係ありません。
本気の方へは本気で対応致します。
谷田部